【シリーズ】Focus on PXC employees :挑戦はいつも現場から。進化し続けるキャリアの軌跡。
(Interviewer:PXC株式会社 UTSUSU編集長 田村 典子)

Interviewee:PXC Inc.
PXC株式会社 執行役員 伊藤 貴大
シリーズ第3回目は、2025年10月1日よりPXCの執行役員に就任された伊藤貴大 氏。
これまでのキャリアや、PXCに入社されたきっかけ、今後の展望などについてお聞きします。
PXCとのお付き合いのきっかけ
― はじめに、伊藤さんがPXCに入社されることになったご縁のきっかけをおしえてください。
(伊藤)株式会社アントロット(https://untrot.co.jp/)の代表で、今年5月にPXCの執行役員に就任した上田さんとのご縁がきっかけです。彼とは友人であり、一緒に起業した仲間の一人であり、ここ4年くらいずっと一緒に仕事をしている戦友のような関係です。
― 上田さんに、「PXCでの仕事も一緒にやらないか?」という感じで誘われたのでしょうか。
(伊藤)はい。上田さん自身がPXCに参画する際に色々と相談されていたのですが、彼の話を聞いたとき、ぶっちゃけ一歩先に行かれたなと思っていて。それが、まさか自分もPXCに誘っていただくことになるなんて考えもしなかったので、その時は、上田さんに負けないよう、僕も何かもう1社起業して頑張ろうと思っていた矢先のことでした。
ビジネス経歴
― それでは次に、伊藤さんのこれまでのビジネス経歴についておしえてください。
(伊藤)大学時代、ゴルフで付き合いのあったプラスチック加工会社の社長さんのもとで、“社内ベンチャー”のようなかたちで仕事をさせて頂きました。そこでは、再利用をテーマにした商品開発と販路開拓の経験をさせていただきました。
― 当時どのような商品をつくられたのですか?
(伊藤)わたしは実家が畳屋なので、まず畳の端材の再利用が頭に浮かびました。そして実際に畳の端材でコースターやランプシェードなどを商品化し、販売しました。
― 学生時代から、ビジネスを実体験されていたのですね。
(伊藤)大学卒業後は、株式会社アコーディア・ゴルフに入社しまして、そこでは、主にゴルフ場事業、練習場事業の運営に携わりました。
― ゴルフ関係の会社に入社されたのは、どのような理由からですか?
(伊藤)もともとゴルフ好きという理由もありましたが、自分はいつか絶対に起業するだろうなと思っていたので、ゴルフを嗜まれる方とのコネクションをつくっておきたいという意図がありました。実際、今でもその時にお会いした方々に助けていただくことや、仕事で繋がっていることが多いです。

― そのゴルフ関係の会社さんを退社されて、その後、ご実家の家業を継がれたわけですね。
(伊藤)はい、2017年に実家の畳屋に入社しました。でも、実はもともと父親からは家業を継ぐことを反対されていたんですね。
― そうなんですか?親は子供に家業を継いで欲しいけど、子どものほうは継ぎたくない、というのは、よく世間で聞くお話ですが、伊藤さんの場合はその逆なんですね。
(伊藤)はい。父親からは、「お前じゃ無理だ、お前の才能では絶対出来ない」と言われていまして。
― そういう意味での反対ですか。職人気質の厳しいお父様なのですね。
(伊藤)はい。本当に怖くて、当時は父親に会うだけで震えがくるほどでした。そんな感じでしたから、当然すぐには入社させて貰えず、先ずバイトから始めろと言われました。バイトで頑張って、従業員さんたちに認められたら、そのとき社員にしてやると言われて、1ヶ月間めちゃくちゃ頑張って働いてようやく入社できた感じです。その後も、いろいろとやりたいことがあって、それを父親に提案するたびに殴られたりしてましたね(笑)。
― 昭和の頑固オヤジって感じですね。最近では、家庭で甘やかされて育ったことで、外でまともに働けない成人が多いなんて話をよく耳にしますが、完全にその逆ですね。

(伊藤)畳屋自体、時代的には斜陽産業と言わざるを得ない事業ですし、実際どんどん売り上げも落ちていましたので、父親としては、生半端な考えで事業を改善することなど絶対に無理だと思っていたようですね。でも、わたしとしては、やり方次第でまだ伸びる部分があるとずっと思っていたんです。まず、新規で問合せと発注を受けられるサイトを、補助金制度を利用して開設しました。それも何回か父親に殴られながら(笑)。
― お父さん、すぐ殴る…(苦笑)。
(伊藤)そう。殴られて「電気代払え!」って言われて。会社のためにつくったサイトなのに、親父のあまりの勢いに、そのサイト制作に掛かった電気代を思わず会社に支払うところでした(笑)。予算も本当にギリギリでやっていたので、そのサイトの制作費用も補助金が下りるまでどうしたものかと困っていたら、近所のミヤゼットというバブルジェネレーターを開発した社長がお金を貸してくれまして。結果、今、そのサイトから月60件以上の問い合わせがあります。需要はやっぱりあったんですよね。でもそれまでガチ職人の父親が、職人をしながら経営していて、そういう状況で、新規の案件を獲得するという考え自体も、そのアイデアをかたちにする術も、父親には無かったというだけで。結局、一年目から、そのサイトで1,300万ぐらい売り上げました。そして、このことが、最近の時勢として面白いということで、当時、朝日新聞に記事として取り上げられました。見出しに「父子対決」って書かれてましたね(笑)。
― それはいつ頃ですか?
(伊藤)2022年頃だと思います。その朝日新聞の取材記事も、それこそアントロットの上田代表(兼PXC執行役員)に戦略的広報として動いて貰って、それで掲載されたんですよ。
― そうだったんですね。
(伊藤)はい。で、年代が前後しちゃいますけど、畳屋で取締役に就任した2020年に、水産業*で起業しまして、今でもそこで牡蠣養殖をやっています。
*一般社団法人隠岐の島振興協会(https://oki-online.or.jp/about/)
― 水産業ですか⁈ ゴルフ企業勤めから、そのあと水産業を起業するという思考が、すこし理解できませんが、どういった経緯で立ち上げられたんでしょうか?
(伊藤)僕、魚が好きなんですよ。それで、自分が魚好きなルーツって何だろう?と思って考えたら、近所に島根県の隠岐の島町出身の方がいらっしゃって、その方がよく魚とかサザエとかアワビをくださって、それで魚介が好きになったことを思い出したんです。そんなこともあって、よくその隠岐の島に遊びに行っていたんです。そこで、海に潜って魚介を銛で突いたりしてたんですけど、ある日、漁師と魚突きバトルをして、僕の方が巨大魚を突いたんですよ。「お前の方が上だなー」なんて言われて、そんなこんなで、なぜかそこの地場の方と一緒に水産会社を立ち上げることになって。親父からも、会社を一人でやってみろって言われてたこともあって、立ち上げました。
― へぇー。伊藤さんのビジネス経歴は本当に多岐に渡りますね。このインタビュー記事だけだと、ちょっと把握仕切れないかも知れないので、末尾に伊藤さんの経歴を分かりやすくまとめた図表みたいなものを入れた方が良さそうです(笑)。
(伊藤)そうかもですね(笑)。ビジネス経歴というと、建築の分野でも顧問として入っている会社があります。僕、建築士でもあるので。
― へぇー。もう、へぇーしか出ませんが(笑)。
(伊藤)最近、自分でも経歴を説明するのが難しくなってきましたね(笑)。なので、周りの方たちは、もっと分からないと思います。水産業の会社で、うちの魚の品質が高いということで、ミシュランの三ツ星店に仕入れて貰っているんですが、僕が全くそのお店に顔を出さないのでお店の方が挨拶しに来るんですよ。来社されたいって連絡が来るので、「ここにいます。」って住所を伝えるんですけど、その住所が畳屋になっているので、「教えて頂いた住所、違っているみたいです。」って連絡が来たりしています(笑)。そろそろ自分の経歴を資料化しないとですね。
― いろんなことをやってる人がなぜ成功するか?ということって、やらない人からすると実はよく分からないと思うんですよね。でも、そこにこそ成功の鍵があるんだろうなと思います。先ず、とにかく常に動いていて、それに伴って多くの人に会う。しかも漠然と動いたり人に会ったりしているようで、実は「これをやったらこういう展開になるかな」っていうことを予測しながら動いていますよね。それこそ無数の点と点が線で繋がっていくことで生まれるアイデアだったり成果ですよね。
(伊藤)そう、まさに繋がってくるんですよね、僕はそれが面白くて仕方ないです。最初に起業した水産業の会社なんて、大学の先生とかに話したら、「バカじゃないの?」「家業の畳とも親和性がないだろう」って言われましたけど。でも、水産業の会社から魚を仕入れてくれている取引先って、和食屋さんとかお寿司屋さんだったりするので、畳を変えたいって言ってくれることが多くて。
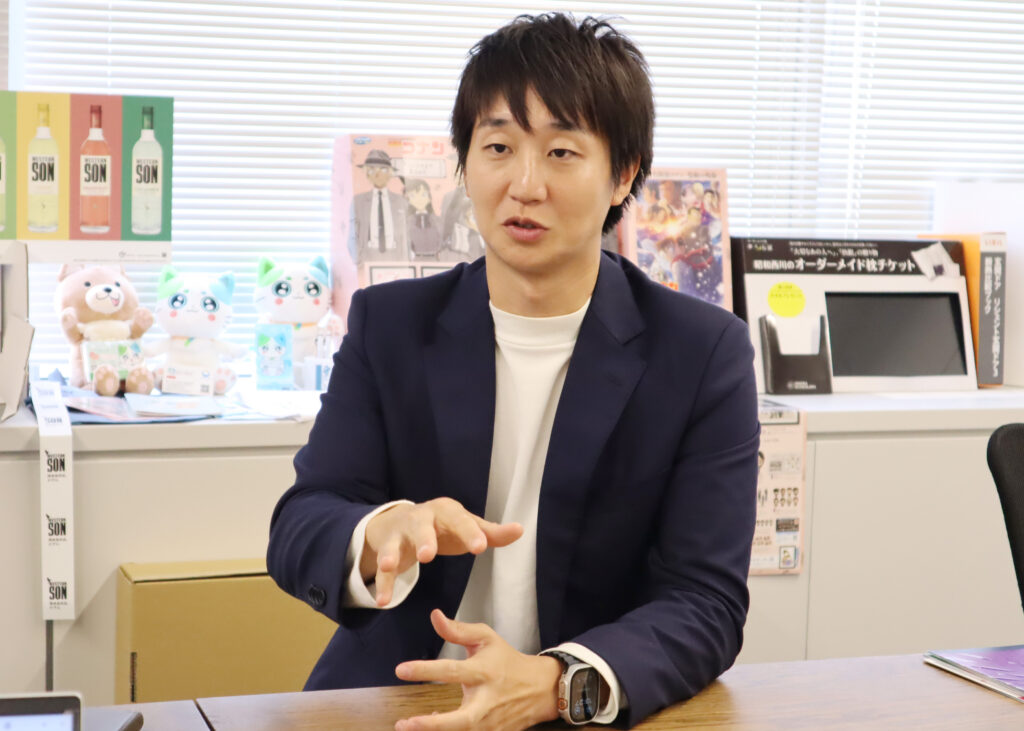
― なるほど、そうですよね。
(伊藤)それと、株式会社ミヤゼット(https://miya-z.jp/)という鉄加工会社との関わりが出来たことで、その会社の事業で僕が開発に携わった装置「バブルジェネレーター」を畳の開発に転用して、その結果、今うちの畳屋はどこよりも強くて安い畳を提供できています。
― その、株式会社ミヤゼットさんで、開発した装置の詳細については、メディアの記事を参照させていただきますね。
※東海 ミヤゼット 魚の鮮度保持に技 /愛知
自動車部品の加工で培った技術が新たな可能性を生み出す。愛知県東海市の部品メーカー「ミヤゼット」が魚の鮮度を保つ洗浄装置を開発し漁業者に好評。
(https://mainichi.jp/articles/20231213/ddl/k23/020/106000c )
― その、伊藤さんがミヤゼットさんで新規事業として開発した装置を使って、家業の畳屋さんでも新しい畳を生み出したお話をお聞かせいただけますか?
(伊藤)はい。僕が水産会社をやっているということもありましたが、隠岐の島町で海に潜ったときに、牡蠣殻の不法投棄ゴミがすごいことに気づきました。隠岐の島町は離島なので、焼却にかかるコストもとても高くて、どうしたものかと行政からも相談があったんです。そこで、この牡蠣殻をなんとかできないかと考えたのがはじまりです。そもそも牡蠣殻って炭酸カルシウムなので、それを畳に混ぜたら低コストで強度の高い畳ができるんじゃないかと思って実際に挑戦しました。一番の課題は牡蠣殻に付着した細かいゴミや不純物の分離でした。当然、最初はうまくいかなくて、そこで威力を発揮したのが、わたしがミヤゼット社で開発に携わった「バブルジェネレーター」です。牡蠣殻をバブルジェネレーターでナノ洗浄したら、驚くほどピカピカツルツルになりました。そうして見違えるほどきれいになった牡蠣殻を粉砕して、低コストで炭酸カルシウムを利用して出来たのが、今うちの畳屋が持っている強くて安い畳です。
― 伊藤さんの取り組んできた経験という点と点が、線で繋がって生まれた成果というわけですね。無から有を生み出すことはもはや難しいと言われて久しいですが、今の時代でも、新しいものを生み出すことは、視点を変えれば幾つもあって、それは開発者の経験と知識、アイデアとひらめき、さらにその人を取り巻く人と人との繋がりによって生まれ得るということですかね。
(伊藤)そうですね、おっしゃるとおりだと思います。
仕事をする上で大事にしていること
― 次に、伊藤さんが仕事をする上で大事にされていることをおしえてください。
(伊藤)僕が仕事をする上で大事にしていることは、一緒に仕事をする相方とか仲間です。その判断基準として、その人と旅行に行って一緒に風呂に入れるかどうか、っていうところを重視しています。この論には賛否あるんですけど(笑)。でも要するに、仕事を一緒にする人とは、仲良くなれる前提じゃないと無理だなと思っていまして。そこを大事に取り組んできて、今のところ大きな失敗をせず、いろいろと立ち上げられているので。基本的に仲良くなれる人を集めて、そこでビジネスを育てていくことを大事にしていますね。アントロットの上田さんもそうですけど、結構、一緒に遊びに行きますしね。そこで移動中、仕事の話もしますし。遊びと仕事で人間関係を分けないほうが仕事は楽しくなると思っています。むしろ仲良くなれれば、その人との仕事は絶対成功すると思っています。
― なるほど。ありがとうございます。一緒に仕事をする人との関係性の他に、仕事をする上で大事にしていることが何か他にもありますか?
(伊藤)内製化ですかね。外注を極力使わないよう頑張っています。

― 内製化を重視する意図はどういったところでしょうか?
(伊藤)昔と違って今はお客さんもクライアントも業界側の事情や情報をよく知っていて、その上で判断や評価をしているので、その仕事が内製なのか外注なのか、結構気にされているように感じています。なので、BtoBでもBtoCでもそうですけど、「自社内で出来ますよ」、「自社に職人・技術者がいますよ」っていうのが、その会社の強みになると思うんです。
― そのあたりのビジネス上で大事にしていることって、ある意味、その方の持つ戦略と戦術なんだと思うんですよね。皆さん独自にそれぞれが持っている成功の秘訣といいますか。なので、やっぱり世代によっても考え方が大きく異なりますしね。その大事にしている秘訣が違うからこそ、ビジネスの世界で、ときには勝敗を分かつ結果に至り、また良い意味で切磋琢磨が生まれる。でも、最終的な結果は多くの要因によって全然変わってくるし、先々のことは誰にも分からないので、正しいとか正しくないとかいうことではないんですよね。平たく言うと、まさに“その人らしさ”っていうことなんだと思います。伊藤さんは、とにかく“人”を重要視しているということですね。
現在、精力的に取り組まれていること
― 多くのビジネス経歴をお持ちになる伊藤さんですが、今現在、精力的に取り組まれていることをおしえていただけますでしょうか。
(伊藤)今、精力的に取り組んでいることとしては、大きく2つあります。まず1つ目は、「社長を育てる」ということです。起業した水産会社は、今いる役員にもうじき社長職を譲りますし、鉄加工の会社にも、ゆくゆくは社長業を担える人材が必要だと感じています。顧問で入っている設計会社も同様ですね。20代後半から部下の人材育成はそれなりにやってこれたと思っているので、今後30代からは、会社をしっかり経営できる社長を育てたいと思っています。それは、経営経験を有する人間が、さらに経営者を傘下に置くことで、ビジネスの骨格がとても強固になるという感覚が、自分の中で掴めつつあるからです。なので、今はそこを一番頑張っていますね。
あともう1つは人脈づくりです。今までは、仕事のメリットだけを考えた人脈づくりが本当に苦手だったんですけど、PXCという会社に参加させていただき、自分にとっても次のステージに向かう中で、今まで自分が付き合うことの無かった人たちとの人脈づくりも精力的に取り組んでいこうと思っています。
― 多くの人と出会って、その中でどのお付き合いを大事にするかということは、あとで自分でいくらでも取捨選択ができるので、そういう意味では、人との出会いを自ら減らすよりは、増やすことの方がビジネスの可能性は広がると思いますよね。
今後の展望
―最後に、伊藤さんの今後の目標や展望をおしえてください。
(伊藤)ずっと心に掲げているのは、日本の生産性を自分の力で1ミリでも向上させたいという思いです。それには、もっと日本の若者に活躍して欲しいという思いもあって、今できることとして、自分が関わっている会社ではインターン制度を積極的に導入しています。それと、これは野望ですが、今の日本の大企業は、世界と比較すると圧倒的に競争力を失っているので、旧態依然とした大企業の成功を中小企業の力でひっくり返してやりたいというのが、やってみたいことの一つですね。これから日本は社会主義化していくと思いますし、少子高齢化の日本は、成人一人当たりの生産性を絶対に上げていかなければならないわけで。勿論その解決方法としてAIの活用による自動化が進んでいくのだと思いますが、それでもAIでは対処できないことが必ず出てくると思うので。日本が数少ない大企業に依存しない国になる為に、柔軟性とスピード感を持って、ビジネスをドライブさせていける人たちと、今の日本の大企業には成し得ない成果を実現していくという壮大な夢、それが実際に叶うんじゃないかって、今はそんなことを思い描くのが、とにかく楽しくて仕方ないです。

― 本日は、伊藤さんの大変興味深い経歴のお話から、今後の素晴らしい展望まで幅広くお話をお聞かせいただきました。実は、本日伊藤さんにお話いたただいこと以外にも、まだ経歴が他にもありますので、記事の末尾に「伊藤貴大 経歴」のまとめを掲載させていただきます。
伊藤さんの数多くの活動の中で、PXCはまだひとつの点に過ぎないかも知れませんが、これまで同様、この点を他の点と繋いでいくことで、今までPXCには無かった価値や成果を生み出されていくことを期待しております。お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
(執筆 田村典子)
【まとめ】PXC株式会社 執行役員 伊藤 貴大
伝統産業・地域産業から先端DXまで、幅広い事業を同時並行で推進する次世代型経営者。
「地域×テクノロジー」「伝統×革新」を軸に、複数の立場を横断しながら社会課題と事業成長を両立。



\UTSUSUに関するご質問・ご相談/



