【シリーズ】Focus on PXC employees : 緻密な計算と細部にわたる創意工夫で守りきる“品質”と“顧客満足度”
(Interviewer:PXC株式会社 UTSUSU編集長 田村 典子)

Interviewee:PXC Inc.
ハンソクエスト事業G SPユニット4 業務購買チーム
児玉 裕希、大久保 孝一
シリーズ第2回目は、ハンソクエスト事業グループにおける製造案件の屋台骨「業務購買ユニット」メンバーへのインタビュー。業務購買ユニットは、製品の品質管理だけでなく、細部にわたる創意工夫でクライアント満足度を保つ役目を担い、さらには購買機能として製品の品質とコストのバランスをコントロールする重要なポジションです。また同時に各製造工程を依頼するハンソクエストメンバー企業様との関係を円滑に保つなど、その役割が多岐に渡る云わばハンソクエスト事業グループの要ユニットです。本日は、その業務購買ユニットメンバーのお二人に、仕事の難しさや遣り甲斐、今後挑戦したいことなどについてお聞きました。
PXC入社の動機やきっかけについて
―お二人は新卒でPXCに入社されましたが、PXCに入社した動機やきっかけを教えていただけますでしょうか。児玉さんが少し先輩になりますよね。
(児玉)はい。わたしは2016年に入社して今年で10年目を迎えます。学生時代にドラッグストアでアルバイトをしていまして、そこで多くの時間、手書きのPOPを書いたりメーカーから送られてくる販売什器を組み上げたりしていました。その時に思ったのが、今でこそオンラインで買い物する人が多いと思いますが、当時は、人は結局のところお店に行ってから何を買うかを決めることが多いなと感じていて、店頭販促物の重要性みたいなものを知らず知らずに学んでいたように思います。ですので、当時アルバイトの身ではありましたが、お店の手書きPOPを書くときには、その商品のどういったところがアピールポイントなのかを理解するために、ちゃんと商品を調べた上でつくるように心がけていました。そういった経験をしていく中で、モノづくりとしての販促関係の仕事は面白そうだなと思いはじめたのが今の仕事に興味を持った動機になります。PXCに入社した経緯は、大学の進路相談室にPXCの求人が来ていて、もともと先生に販促物制作に関わる仕事をしたいと相談していたので、「この会社は、やりたいことに近いんじゃない?」と紹介していただき、面接を受けて入社したという流れです。
―それで言うと、学生時代にやっていたアルバイトをきっかけに、将来やりたいことが概ね見えてきて、その進路の意志をきちんと先生にも相談していたので、おのずとその道が開かれたということですね。
(児玉)そうですね。進路でいうと当時は販促も「広告」っていう大枠に入ってしまっていたので、先生からは、大手の広告代理店でCM制作とかの仕事はどうですか?とか聞かれていたんですけど、どちらかというと店舗にある販促物が作りたいです、と回答をしていたので、ごく自然な流れでPXCに入社したかたちです。
―珍しいですよね。恐らく学生時代にドラッグストアで手書きPOPをつくったり、什器を組み上げたりした経験がなければ、あまり知り得ない業界だと思います。
(児玉)そうですね、わたしもアルバイトでそういった仕事をしていなければ、店頭販促に対してそこまで意識はしなかったと思います。今、まさにPXCで制作している什器なんかも、当時、「この什器は作りづらいな…。」とか、実際に感じながらやっていたので。
―買い物に来る人たちの多くは、販促物そのもの自体を殆ど意識していないのですが、販促物の有無による売り上げの影響はかなり大きいですよね。実際そういったデータもたくさんあります。PXCは総合プロモーション代理店で、プロモーションに関する仕事は様々な部門と社員のスキルで複合的に行っていますが、中でも店頭販促物の企画・制作・製造は、創業時から続いている事業で、私たちにとってとても重要なノウハウといえますね。
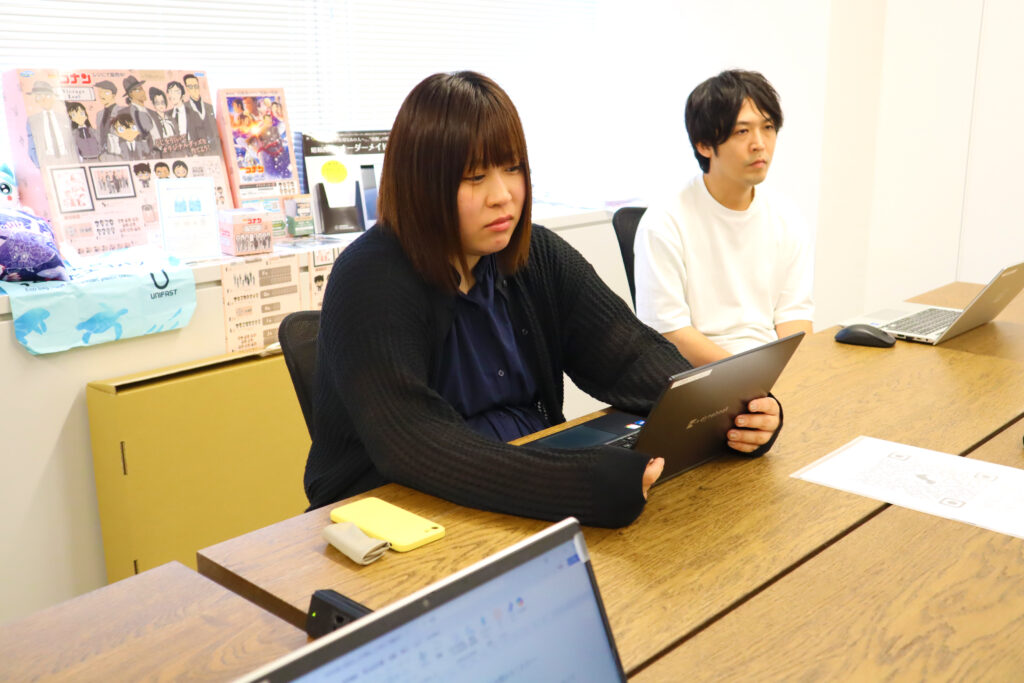
―それでは、後輩にあたる大久保さんもPXC入社の動機をお聞きします。
(大久保)はい、わたしは児玉さんの2年後輩にあたる2018年4月入社で、今年で勤続8年目になります。PXCに入社したきっかけは、学校主催の就活セミナーの中に、当時PXCの前身であったトスグループが参加されていて、当時トスグループの総務で現PXC管理グループ ユニットリーダーの吉田さんと、わたしの大学の先輩で、現ハンソクエスト事業グループで、セガさんやフリューさんなどの大手メーカーの担当プロデューサーをされている鈴木さんが二人でいらっしゃっていて、お二人の話を聞いて、先ずこの会社の“人”は面白そうだなと思いました。特に鈴木さんはとても面白い方という印象でした。業種的なところで言うと、その当時、本当に漠然とでしたが、ものづくり的なことをしてみたいという気持ちがあったので、トスグループの会社概要を読んで、面白そうだから応募してみようと思い、当時トスグループのひとつだったトスヴェルト社に入社しました。
―大久保さんは、トスヴェルトに入社して、トスグループ3社がPXCとして統合されてから現在のような業務部門に配属になったんでしょうか?
(大久保)わたしはトスヴェルトの所属ではありましたが、工場勤務ではなく、トスマックの営業部隊と一緒に仕事をするポジションで、その当時「プロセス部門」といわれていた部署に配属になりました。その部門で、現在の業務購買ユニットと同じような業務に従事していましたので、仕事内容自体は入社時から大きく変わってはいません。
―なるほど、じゃあ製造のプロセスディレクター歴8年ってことですね。
(大久保)はい、そうなります。
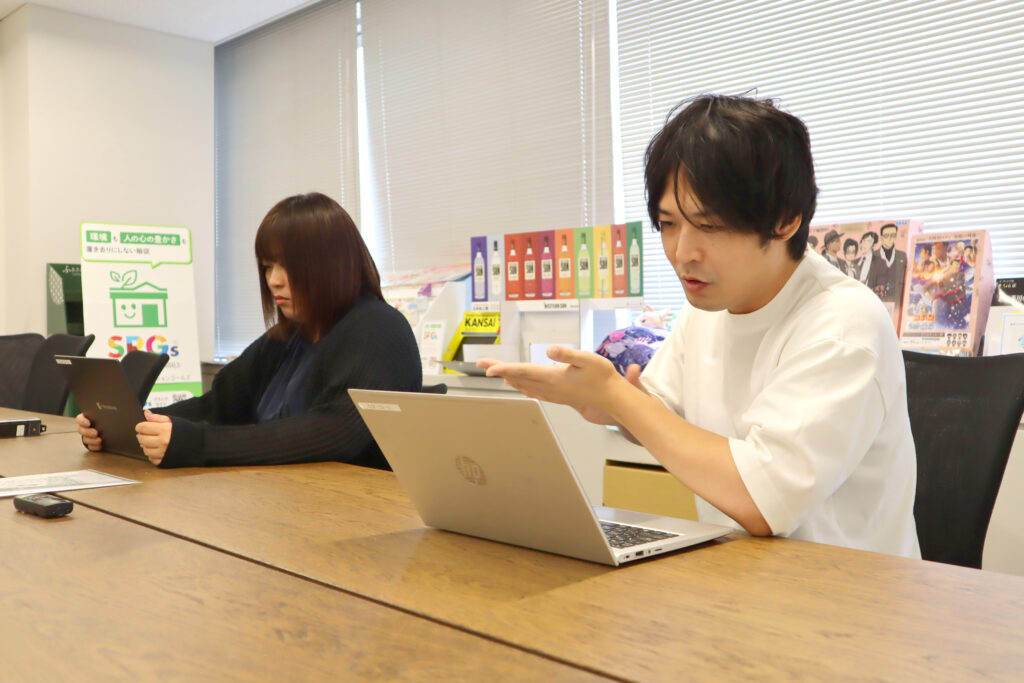
―それで言うと、児玉さんは、以前は店頭販促物案件メインの営業職だったんですよね。
(児玉)そうです、元々は大手代理店・印刷会社担当の営業職で入社しています。
―そうすると、何年かの間は営業だったんですね。
(児玉)はい、入社して2年間は営業でした。
―そうでしたね。営業として担当クライアントを定期的に訪問して、依頼案件を聞いて、という仕事だったんですよね。その後、入社3年目から営業に依頼された製造案件のプロセス業務をメインに、部材やセットの手配とかコスト管理とか、そういう部門に異動になったんですよね。
(児玉)そうです。
―営業職から業務職への役割変更は、児玉さん的にはウェルカムだったんでしょうか。
(児玉)そうですね、もともと店頭販促物をつくりたいという動機もありましたし、当時、営業職は自分には不向きかもしれないと思っていたこともあって、会社からその提案を頂いていて、出来るか分からないけれど挑戦してみようと思いました。
―そうでしたか。それで云うと、児玉さんも2年間とはいえ営業職でクライアントとの折衝を経験しているので、今は業務職ですが、営業が依頼してくる無理難題も“理解してあげられなくはない”っていうところがきっとありますよね。
これまで担当した仕事で印象深かった事柄
―それでは次にお二人の仕事上での忘れられない思い出やエピソードをおしえてください。
(大久保)入社4年目で某大手印刷会社担当チームに配属され、そこで製造業務担当者としてクライアントと直で話すようになりました。その時に、それまで業務だけをやっている環境では良く分からなかったクライアントの“反応”を知ることができたんです。例えば、こういうものを持っていったら怒られるとか、色が悪かったらこういう反応されるみたいな、品質に対する評価を予測できる感覚みたいなものを掴むことができました。このときクライアントの生の反応や高い要求に自分自身が直面したことで、業務担当者として何をすべきかが見えてきたというか、自分で理解した上で主体的に考えて行動できるようになったと思います。この入社4年目での経験が、自分が大きく成長することができた正にターニングポイントでした。
―とても良いはなしですね。そうでしたか。児玉さんは入社して2年間営業をしていた経験があることで、役割が業務に変わっても営業の要望を理解できる強みを持っているのと同じですね。大久保さんは入社以来ずっと業務部門で、3年間はクライアントと間接的にしか関わらない体制で従事してきたわけですが、クライアントと直に接することを経験したことで、それまでの営業を通じたクライアントオーダー対応よりも、かえって効率が良いというか、自分の中でクライアントの要望が腹落ちするようになったということですよね。
―PXCのクライアントは、ありがたいことに大手代理店さんもいれば、大手印刷会社さんもいて、直需の事業会社さんもメーカーさんもいて、しかもその直需の会社さんは超大手企業だったり中小企業だったり、本当に様々ですよね。大久保さんが以前所属していたチームは、大手の印刷会社さんなので、「ここまで拘るんだ」みたいなことへの驚きもあったでしょうし、逆に言うとメーカーさんだと、「結構、知らないことが多いんだな…」みたいなことがあったりしますよね。でもこれって普通に考えれば当然ですよね。クライアントさんの業種業態、担当者さんの部署や役割、年齢によって知識やリテラシーのレベルが全く異なりますので。だからこそ、このクライアントさんであれば、自分の役割として何を最重要事項とすべきか想定する感覚を持つことは、仕事をスムーズに進める上でかなり重要なことだと思います。自分が相対している人がどんな人なのか、相手ときちんと向き合って理解しようとする姿勢こそが、仕事のみならず物事を円滑にする鍵なのだと思います。

―児玉さんはいかがですか。
(児玉)いまでも印象に残っているのが、ヒヤッとしたミスの経験です。製造業務を担当するようになって1年目に発送リストの作成業務があったのですが、この発送リストというものは、情報量が多くて複雑な内容の場合、エクセルの数式を使ってパターンをつくるんです。例えば、2個納品する店舗が一番多い場合それをAパターンに設定して、次に多いのが3個納品であればそれをBパターンというような設計をするんですけど、当時そのやり方を教えてもらったばかりの頃で、そこそこの規模の発送リストを編集した時に、1箇所フィルターをかけ忘れてしまって、情報をぐちゃぐちゃにした状態で伝票発行担当者にそれを渡してしまったんです。私はそのデータの設定を習ったばっかりだったので、自分がそういう事象を起こしていることすら理解していなくて。当時はまだPXCに統合される前だったので、工場がメイン事業のトスヴェルトに伝票発行お願いしていたんですが、その時の担当の方が「あれ、ちょっとこのリストデータなんかおかしくない?」と気づいてくれて、その時はやり直して実際の納品ミスは起こらなかったんですけど、これが例えば路線便の会社とかに直接依頼していたら、おそらく何の指摘も入らないまま凄い数の誤配送が発生していたかと思うと、今思い出しても本当にヒヤッとするミスでした。
―怖いですね。人的ミスっていうのは、なかなか防ぎようがないですよね。機械で自動化できることにもやっぱり限界があるので、結局は人がちゃんと管理しなければならない。そして、ミスや事故を無くすには、一人ではなく何人かで愚直に二重三重にチェック体制をつくることが大事だと思います。依頼された仕事にミスや事故が起こった際、それをリカバーすることがどれだけ大変か。その対応にのしかかってくる負荷とストレスは半端ないですよね。場合によってはコストが持ち出しになって、会社に甚大な損害を与えるリスクすらありますからね。このミスや事故を起こさないことへの意識は、業務部門だけでなく、営業部門や制作部門も含めて、事業部や会社全体で高めていかなければならない課題だと思います。
業務購買としての仕事の難しさや遣り甲斐について
―それでは次に、業務購買部門での仕事の難しさや遣り甲斐について教えてください。
(児玉)製造業務の中で難しいと思う部分は、品質担保とコストのバランス管理です。この内容だとこの金額ではかなり厳しいという案件もあるので、担当営業がどのぐらいの利益を想定しているのかと、作業の内容を照らし合わせて、先ずは自分なりに大体どのぐらいの金額で設定できるかを試算して、その上で発注先を検討するようにしています。この品質管理とコスト管理のバランスを取るのが、業務購買部門の難しさであり最も重要な役割だと思います。ただ、部署の先輩方がみなさんベテランなので、何か困ったらすぐに相談できる環境にはとても恵まれていると思います。
―業務購買部門での遣り甲斐はどんなところでしょうか。
(児玉)業務購買ユニットの中にも個人予算があるのですが、私はこの個人予算があることで目指すものが明確になっています。数字を追っていくのが遣り甲斐というか、分かりやすいなと感じています。
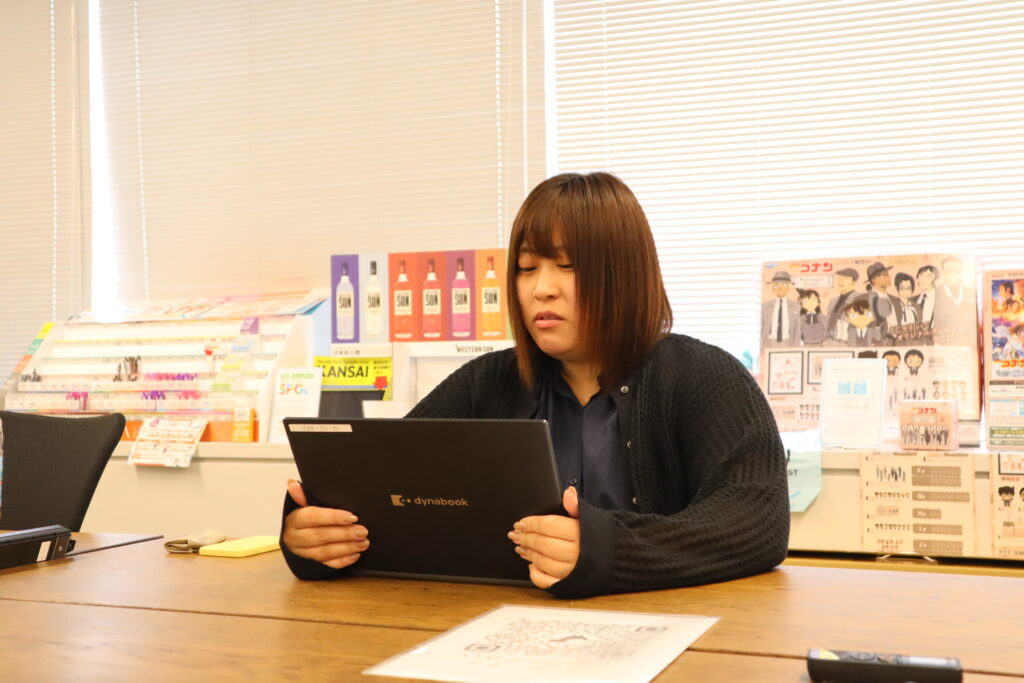
―ありがとうございます。では、大久保さんの思う業務購買部門における仕事の難しさや遣り甲斐をおしえてください。
(大久保)わたしたちのやっている仕事って、言ってみれば、さきほど田村さんが仰られていたダブルチェック機能だと思うんです。実際、わたしたちがやっている業務購買の仕事を、案件を受けてきた担当営業が自身でやることも物理的には可能なわけなので。でも、わたしたちが、担当営業と一緒に役割を分け合って対応することで、モノづくりの精度が上がるんですよね。そうなることで、仕事を直接依頼されている担当営業は、品質管理に対する責任を任せられるという安心が生まれる。なので、わたしは業務購買の担当として、営業の安心感とクライアントの信頼感を生み出すことこそが、自分の遣り甲斐だと感じています。
―なるほど。今のおはなしは今回のインタビュータイトルの内容ズバリですね。わたしたちのような業態において、クライアントが信頼を寄せているものは何か?と考えた時、その答えは、やっぱり事業会社と同様、成果に対する品質だと思うんですよ。もちろん営業とクライアント担当者との関係値も重要ですが、それは「信用」であって、依頼に対する「信頼」では無いと思うんです。どんなに担当営業がクライアントの信用を得ていたとしても、制作・製造したものに問題があれば、途端にその営業の信用は吹っ飛んでしまうので。むしろ、あんなに大丈夫だと言っていたのに、完成したものが全然ダメじゃない!となりますよね。品質こそがお客さんの寄せている「信頼」であって、それ以外の何ものでもないと思います。実際、長年PXCに依頼してくださっているクライアントさんは、間違いなく成果に対する品質に信頼を寄せてくださっているからだと思いますし、そういった意味でもPXCの業務購買部門が、いかにPXCにとって重要な役割を果たしているか分かりますよね。
仕事をする上で大事にしていること
―お二人が仕事をする上で大事にしていることをおしえてください。
(大久保)SP代理店として製造する範囲が広いので、いまだに何かしら新しいことを知る機会が多いんです。ですので「日々学び」といいますか、自分の知識を常に増やし、スキルを高めることにポジティブな姿勢で臨むことを大事にしています。
―PXC社員のスキルが上がることで、PXC社としてのスキルが上がるわけですよね。新しいことを学ぶのは、歳を取ると億劫になる人が多いのも事実ですので、大久保さんの「日々学び」の姿勢はとても素晴らしいと思います。是非その姿勢を大事にしていただき、PXC社の機能向上に貢献していただきたいと思います。
(児玉)わたしの大事にしていることは、当然のことといえば当然のことなんですけど、依頼する協力会社さんに敬意を持って接することです。わたしたちがお仕事を依頼する立場ではあるんですけど、絶対に横柄な態度は取らないと決めて日々仕事をしています。わたしが、このことを大事にしている理由は、わたしはこれまでに、仕事だけでなく人生の中で客観的にみて、「誰か」が「誰か」に対して横柄な態度を取って、そのあとで物事が上手く進んでいるところが見たことがないので。横柄な態度や高圧的な態度をとる人は、一時的には自分の望み通りになっているかもしれないけれど、そうされた側の人は、そのあと前向きな姿勢では、その人に協力しないだろうなと思うので。業務を遂行するにあたっては、PXCの協力会社の方々に助けていただくことが本当に多いですし、協力会社さん無しでは、本当に何もできません。なので、わたしたちが依頼をしている立場ではあるものの、協力会社さんが、仮に間違いやミスを起こしても横柄な態度は取れないし、取るべきじゃないと思っています。それと、一方的にPXCの営業の要望だけを協力会社さんに押し付けることがないようにすることも、わたしが大事にしていることです。コストにしても、スケジュールにしても、必ず一度、営業の依頼内容を自分で噛み砕いて理解してから、どこまでが対応可能な範囲で、どこからが難しい線なのか、それらをちゃんと把握した上で協力会社さんに相談をするように努めています。
―今の児玉さんの話は、クライアントと営業との関係でも同じですよね。勿論、わたしたちはクライアントを選べるような立場ではないですが、所詮人間なので、あまりに横柄な態度や高圧的な態度を取るクライアントに対しては、気持ちの上でやる気が低下してしまいます。一方で、いつも感謝の意を伝えてくださったり、頼りにしてくださるクライアントさんに対しては、その気持ちや期待に応えたいという意欲が高まるのも事実ですしね。それと、児玉さんの言うとおり、間に入ることに存在意義を持つことはとても重要ですよね。そもそも右から左に言われたことを伝えるだけの人なら、その人はいなくてもいいですからね。でも、誰かと誰かの間に入るには、まずバイリンガルである必要があると思います。両者の考えや立場を理解でき、双方が納得いくようにするにはどうすれば良いかを考え、それを双方に提案する。豊富な知識だけでなく多くの経験も必要になる役割だと思います。
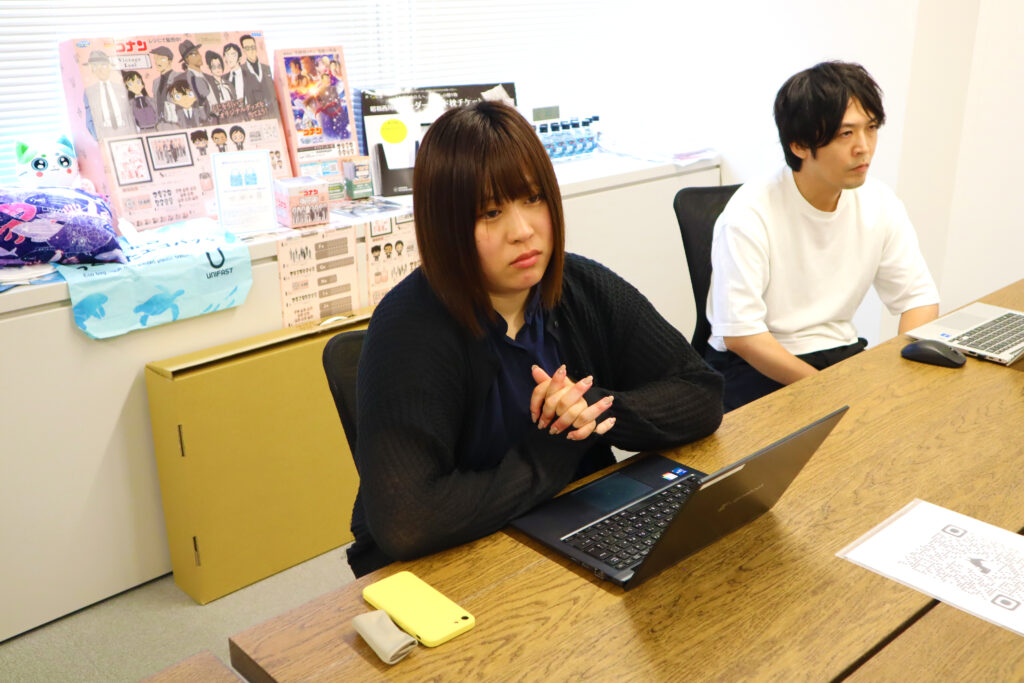
今後の展望
―最後にお二人の今後展望をお聞かせください。
(児玉)わたしは、もう少し積極的に動ける人間になりたいと思っています。基本的に消極的な性格で、あまり自分の意見は言わないタイプなので。
―そうなんですね。
(児玉)はい。ですので、何かがあった時に強く言えないという点では少し課題を感じています。本来であれば、何か間違いがあった時には毅然とした態度で是正しなければならない立場ですし、依頼先とも本当の意味での信頼関係を築いていけないと日々感じているので、今はその部分を改善することを目標にしています。
―バシッと言わなければならない時って、確かにありますよね。ただ、これは本当に難しいと思います。言い方ひとつでは、相手のやる気を無くしたり、嫌な思いをさせてしまうので、結果的に良い方向にいかないという懸念も出てきますからね。これはある種、「言い方」と「伝え方」の工夫だと思います。自分でこのスキルを獲得するというよりも、先輩に助言を頂いたり、ビジネス書のようなものでノウハウを得ることも必要だと思いますね。
―大久保さんの今後の展望はどんなことでしょうか。
(大久保)若手のふりをしていますけど、実は8年目ということで、世の中的にはわたしも中堅になると思いますので、会社の内外ともに頼りにされる存在になることが、今のわたしの目標です。何か難しい仕事があったときに、「それは大久保さんに聞けば間違いないだろう」みたいな、そんなポジションになりたいですね。
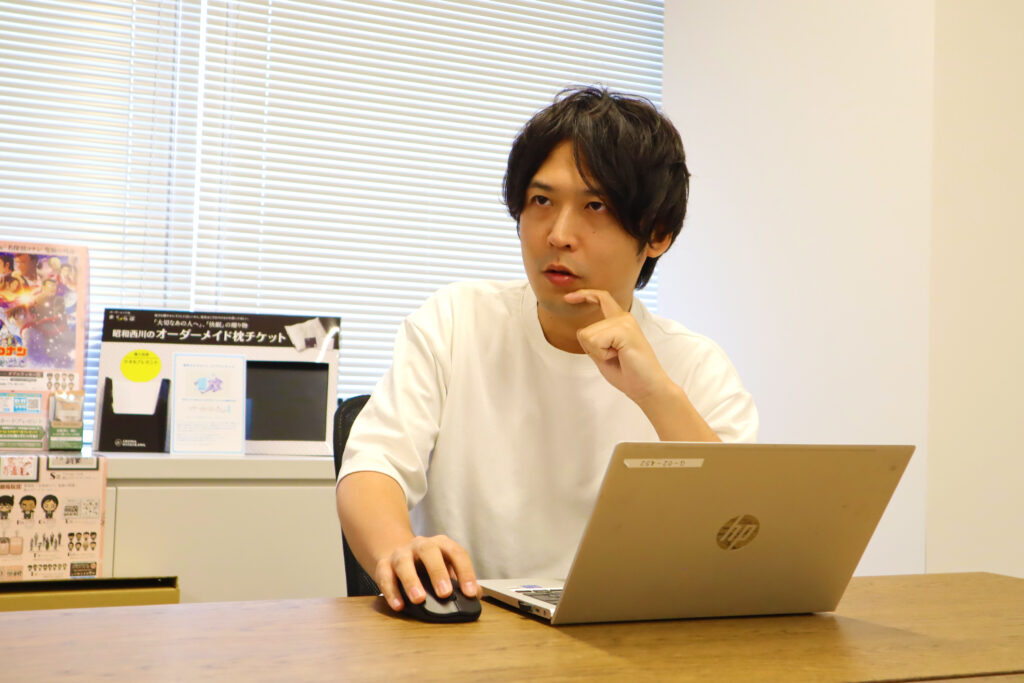
―素晴らしい目標ですね。社内に「これは、あの人に聞けば分かる」という人が多くいることこそが、まさに会社の価値でありノウハウだと思います。
お二人からとても良い話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。これからも、PXCの要の部門メンバーとして、クライアントの為に、協力会社さんの為に、そしてPXCの為に尽力し、活躍されることを期待しています。
(執筆 田村典子)
\UTSUSUに関するご質問・ご相談/



